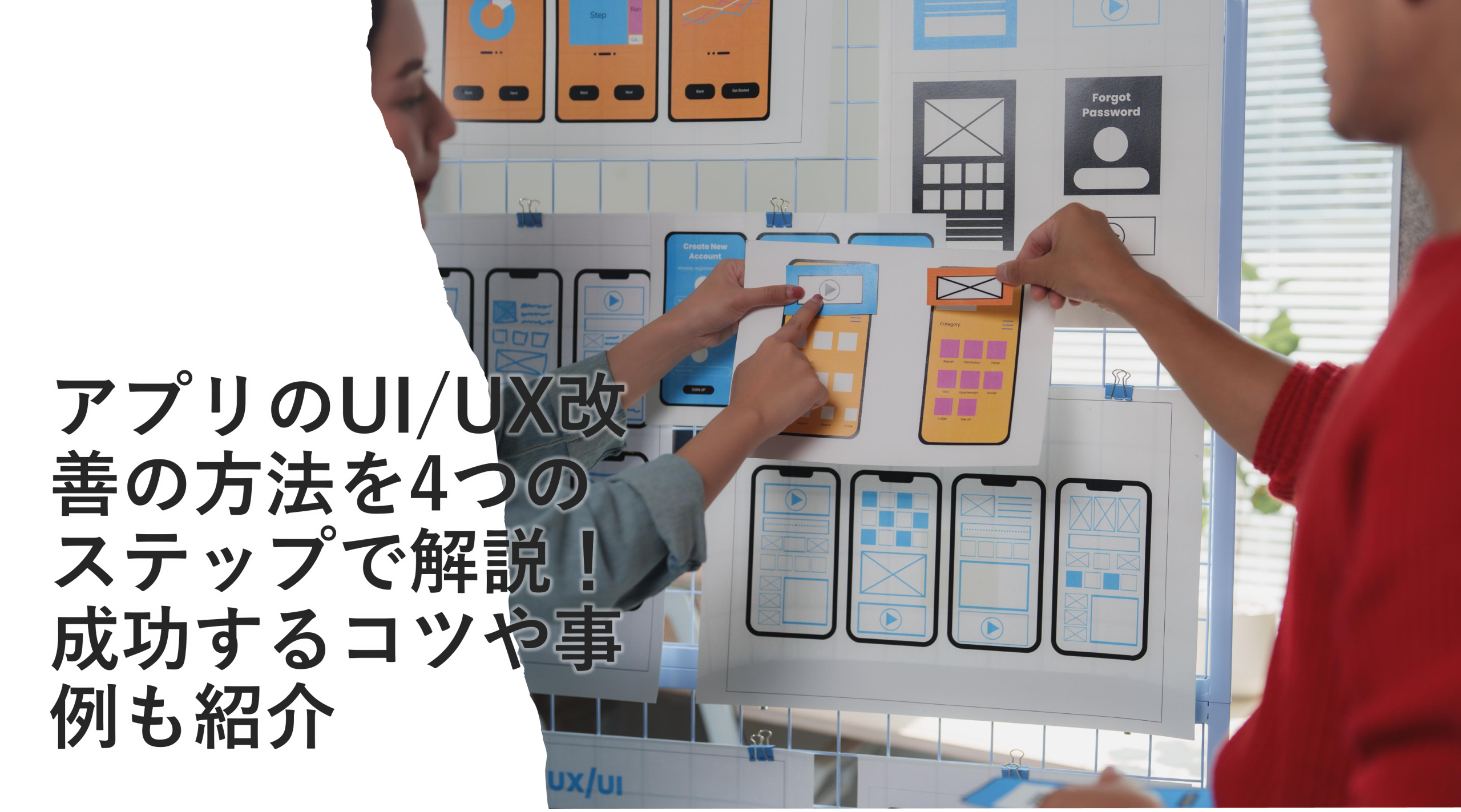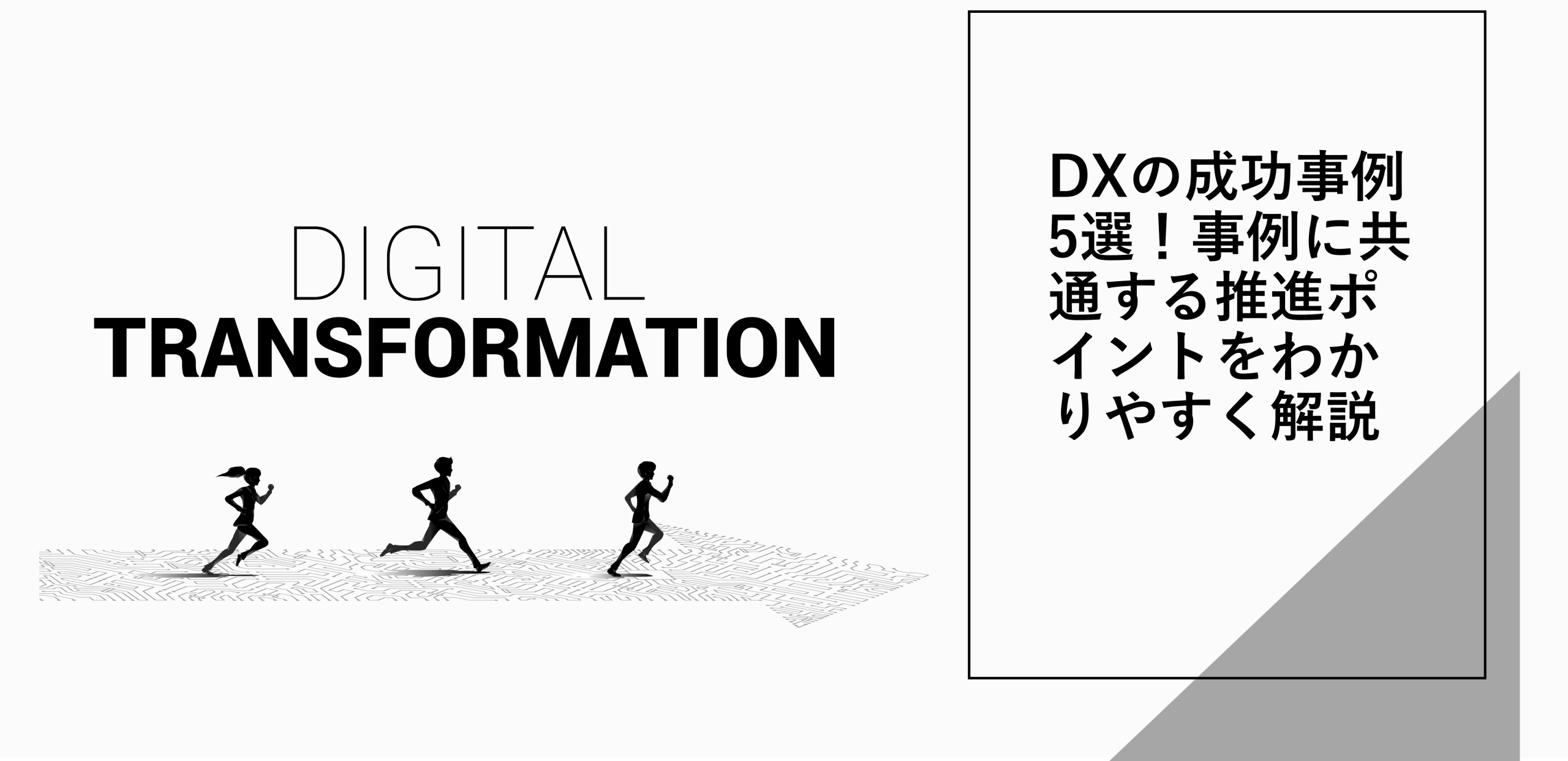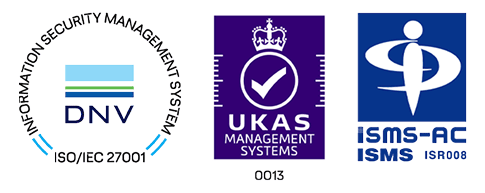リバースエンジニアリングとは?目的や手法、活用されるシーンを紹介

「ソフトウェアの仕組みや構造が分からない」といったシーンで有効な手法が「リバースエンジニアリング」です。リバースエンジニアリングを行いたいものの、具体的な実施方法や使うべきソフトウェアなど、疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
今回は、「リバースエンジニアリングとは何か」をテーマに、基本をまとめてお伝えします。リバースエンジニアリングに役立つソフトウェアも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
ソフトウェアへのリバースエンジニアリングとは
リバースエンジニアリングとは、既存のソフトウェアを分析して、その仕様や設計を明らかにする手法です。
通常のソフトウェア開発では、仕様書や設計書に基づいて開発が進みますが、これらの文書が存在しない、または確認できない場合もあります。そうしたときに有効なのがリバースエンジニアリングです。
この手法は、通常の「設計から開発」への流れとは逆に、完成したソフトウェアを出発点として、内部のコードや構成から仕様や設計の意図を読み取ります。
つまり、完成済みのソフトウェアをもとに仕様や設計を再構築するのが、リバースエンジニアリングの目的です。
ソフトウェアに対するリバースエンジニアリングの主な目的
ソフトウェアに対するリバースエンジニアリングは、さまざまな目的で行われています。ここでは、リバースエンジニアリングの4つの目的について見ていきましょう。
- 属人化の解消
- コードの品質向上
- 脆弱性の特定
- 技術的な調査
属人化の解消
既存のソフトウェアを継続的に運用するうえで、属人化(特定の担当者にしか対応できない状態)は大きな課題です。リバースエンジニアリングは、その解消に有効な手段です。
長年運用されたシステムでは、修正や拡張が繰り返され、最新の仕様や設計を反映した文書が残っていない場合があります。その結果、担当者以外が全体像を把握しにくくなり、引き継ぎや作業分担に支障をきたすこともあります。
リバースエンジニアリングによって、現行のソフトウェアに即した仕様書や設計書を整備すれば、新たな担当者でも短期間でシステムを理解しやすくなります。属人化の解消と業務の標準化にもつながるでしょう。
コードの品質向上
リバースエンジニアリングは、コードの品質向上にも役立ちます。
内部構造が可視化されていない状態では、冗長な記述や構造的な問題に気づきにくくなります。特に、長年にわたって調整が繰り返されたシステムでは、コードが複雑化し、保守が難しくなる傾向があります。
リバースエンジニアリングを通じて構造を把握すれば、重複処理や非効率なアルゴリズムなど、潜在的な問題を見つけやすくなります。
問題を改善することでコード全体の品質が向上し、保守にかかる負担やコストの削減にもつながります。
脆弱性の特定
リバースエンジニアリングは、ソフトウェアに潜む脆弱性(セキュリティ上の弱点)の特定にも有効です。近年はサイバー攻撃の脅威が高まり、ソフトウェアの安全性確保が重要になっています。
特に、古い技術で構築されたレガシーシステムでは、新たな脆弱性に対応できていない場合があります。その構造や設計を明らかにすることで、脆弱性への対処が可能になります。
技術的な調査
これまで紹介した3つの目的は、主に自社内のソフトウェアに対するリバースエンジニアリングでした。一方で、他社製品やオープンソースソフトウェアを対象とした技術調査の目的でも、リバースエンジニアリングが行われるケースはあります。
外部のソフトウェアでは、詳細な仕様や設計が公開されていない場合が珍しくありません。そこで、リバースエンジニアリングによって内部の仕組みや構造を分析すれば、使われている技術について把握できます。
ただし、特定の企業や個人が開発・提供しているシステムやサービスに対してリバースエンジニアリングを行う場合は注意が必要です。
利用規約で禁止されているケースも多く、著作権の侵害につながる恐れがあります。実施前には必ず利用規約やライセンス条件を確認し、規約違反とならないよう十分に配慮して進めましょう。
ソフトウェアに対するリバースエンジニアリングの手法
リバースエンジニアリングの手法は、主に「静的解析」と「動的解析」の2つに大別されます。それぞれの手法について見ていきましょう。
静的解析
静的解析とは、ソフトウェアを実行せずにコードの内容を解析する手法です。主にソースコードやバイナリファイル(実行可能ファイル)を解析しやすい形に変換し、そこから処理の流れや構造を読み取ります。
具体的な方法としては、逆アセンブル(機械語をアセンブリ言語に変換する手法)や、逆コンパイル(バイナリファイルを元のコードに近い形へ戻す手法)などがあります。いずれも、実際の動作をともなわずに解析できる点が特徴です。
ただし、逆コンパイルなどで生成したソースコードは、可読性が著しく低いケースが少なくありません。この場合、人間が解読することは容易ではなく、リバースエンジニアリングには高度なスキルや経験、多くの労力が求められます。結果として、作業期間やコストが増大する場合もある点に注意が必要です。
静的解析は、コードの品質調査や技術的な調査など、さまざまな目的で行われます。
動的解析
動的解析は、ソフトウェアを実際に動作させ、その挙動から内部の構造や処理を解析する手法です。入力データに対する出力データの変化や、実行時のメモリ使用状況・CPU状態など、ソフトウェアの挙動を詳細に調べます。
具体的な方法としては、デバッギング(専用のデバッガを用いてソフトウェアの詳細な動作を追跡する手法)やネットワーク解析(外部とのネットワーク通信を監視・分析する手法)などがあります。
動的解析は、ソフトウェアを動かさないと発見が難しい問題も検出できる点が特徴です。脆弱性の検出やマルウェアの挙動確認といったセキュリティ分野でも広く行われています。
リバースエンジニアリングに役立つソフトウェア3選【フリー/有料】
リバースエンジニアリングを行う際には、専用の解析ソフトウェアが欠かせません。ここでは、静的解析や動的解析に役立つ代表的なツールを3つ紹介します。
JD-GUI
「JD-GUI」は、多くのシステムに採用されている「Java」で開発されたソフトウェアの逆コンパイルに特化したツールです。クラスファイル(*.class)やJARファイル(*.jar)を元のJavaプログラムに近い形で復元できます。
名前の通り、GUI(視覚的な操作画面)を備えているため、慣れていない方でも直感的に操作しやすいのが特徴です。Javaを扱うシステム開発において、属人化の解消を目指すケースなどで役立つでしょう。
SonarQube
「SonarQube」は、「Java」「C#」「Python」といった幅広いプログラミング言語に対応している静的解析ツールです。コードに潜んだバグや脆弱性、保守性を損なう問題点などを自動的に検出・可視化します。
「COBOL」のような昔ながらの言語にも対応しているため、幅広い開発現場で活用されています。ただし、静的解析を行うためには、事前に変換されたコードが必要です。そのためバイナリファイルを解析したい場合には、逆アセンブルや逆コンパイルに対応した別のツールを併用する必要があります。
Jitera
「Jitera」は、AI(人工知能)によりソフトウェア開発の自動化・効率化を支援するツールです。コードの自動生成といった通常の開発支援機能に加え、既存コードから設計書を生成するといったリバースエンジニアリング寄りの機能も備えています。
設計書が存在しない、いわゆるブラックボックス化したシステムでも、コードを通して全体構造を迅速に把握できます。「コードは残っているが、仕様が不明」といった場面で活用しやすいツールです。
まとめ
リバースエンジニアリングとは、既存のソフトウェアを分析し、その仕様や設計を明らかにする手法や技術のことです。システムの可視化による属人化の解消、コードの品質向上、脆弱性の特定、技術調査など、さまざまな場面で活用されています。
リバースエンジニアリングには、専用のソフトウェアを活用することが一般的です。ただし、正確に進めるためには専門知識や経験が求められ、ノウハウがないと対応が難しいケースもあります。
バルテス・イノベーションズでは、専門エンジニアによる高品質なリバースエンジニアリングサービスを提供しています。社内に適任者がいない、進め方が分からないといった場合は、ぜひご相談ください。