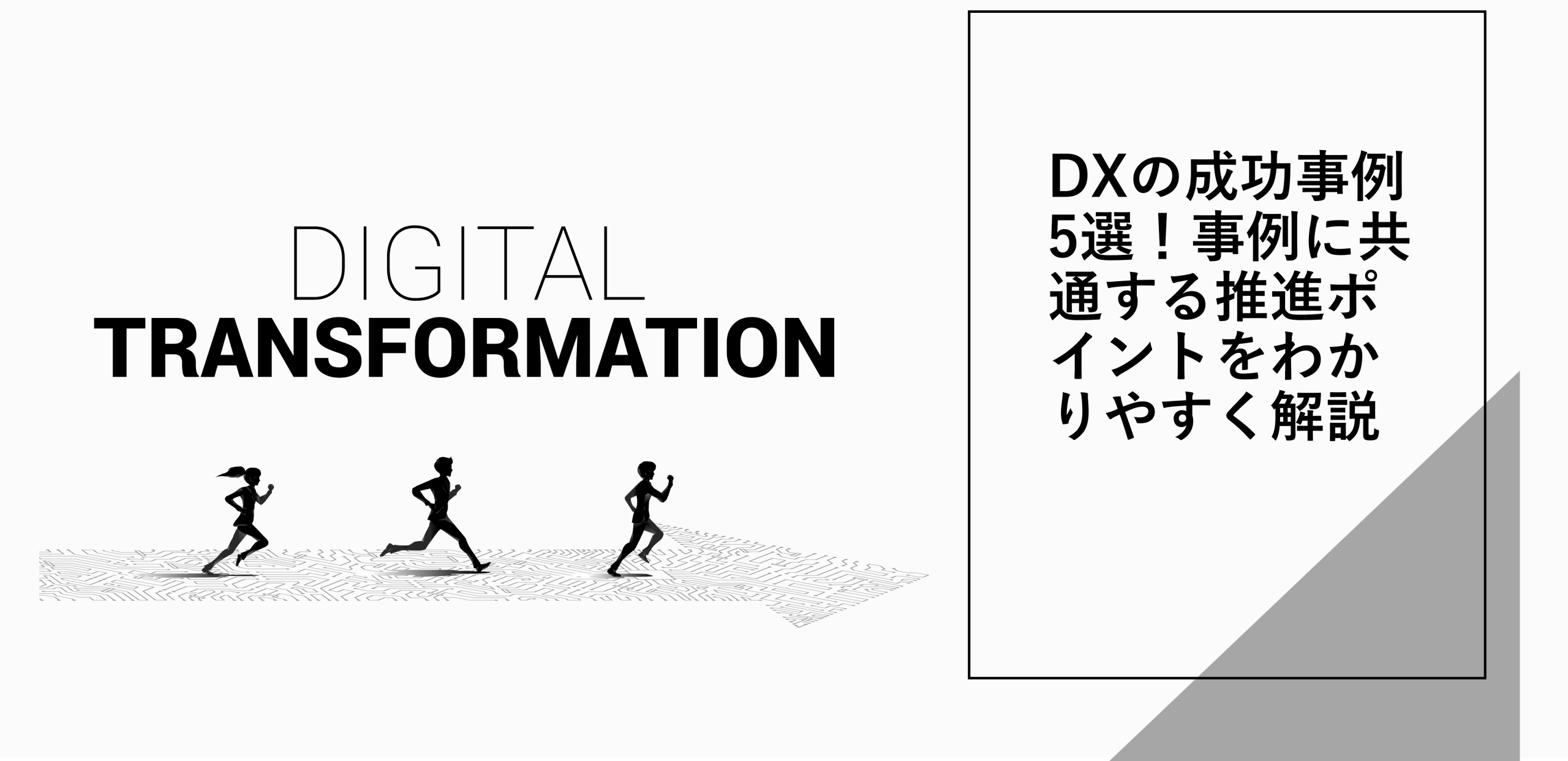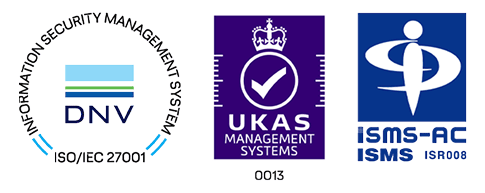アプリのUI/UX改善の方法を4つのステップで解説!成功するコツや事例も紹介
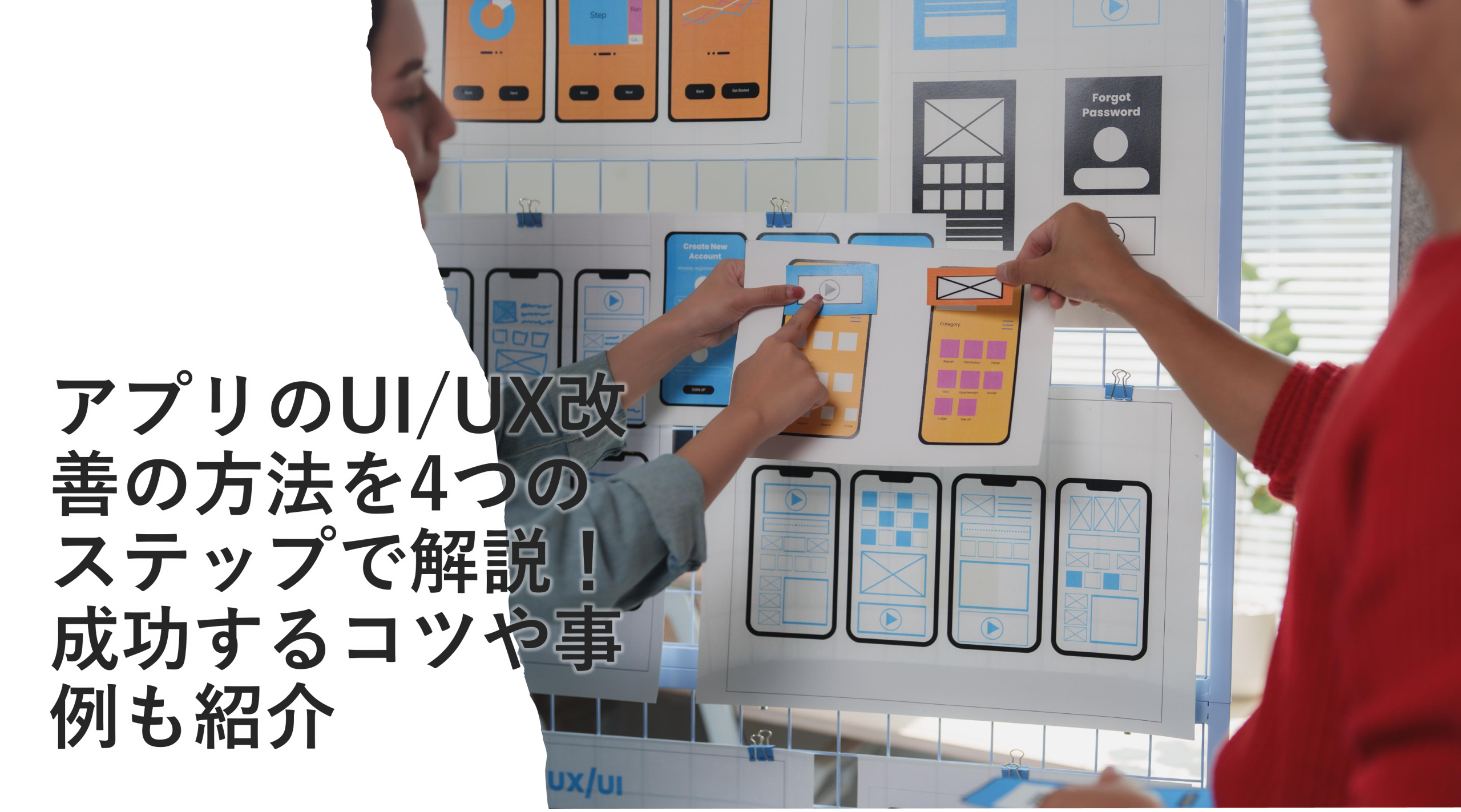
アプリを公開しても利用率が上がらない、機能を追加しても期待ほど使われないと悩むケースは少なくありません。UI/UXの質はサービスの成果を大きく左右します。見た目を整えるだけでは不十分で、ユーザーの行動や心理を踏まえた体系的な改善が欠かせません。
本記事では、UI/UXを効果的に改善するための4つのステップを順を追って解説します。
UI/UXの改善とは?
本校で述べるUI/UXの改善とは、以下の観点でより快適で使いやすくするために見直す取り組みを指します。
- UI:画面やデザインの見た目
- UX:利用全体を通じた体験
機能が優れていても、操作が複雑であったりデザインが見づらかったりすれば、ユーザーは不便を感じて離れてしまいます。したがって、UI/UX改善は「顧客満足度の向上」「継続利用率の確保」「競合との差別化」という3つの点で欠かせない取り組みと言えます。
UI/UXの改善をするメリット
アプリのUI/UXを改善するメリットは、見た目だけの改善ではありません。主に以下のメリットがあります。
- 継続利用率が伸び、LTVが向上する
- 無駄機能の削減と優先度の明確化で、開発投資のROIが改善する
- 使いやすさが口コミ・レビューに反映され、ブランド信頼や評判が向上する
上記のようにUI/UXを体系的に磨くことは、目先の見栄えを整える作業ではなく、集客効率やコンバージョン、継続率など多面的に効く事業の基礎体力づくりです。限られたリソースでも優先度の高い改善点に集中することで短期の数値改善と中長期の競争優位を同時に実現できる点がメリットです。
UI/UXを改善する4つのステップ
UI/UXを改善する際は、やみくもに進めるのではなく以下4つのステップで進めましょう。
ステップ①ユーザビリティテストやアンケートを実施
UI/UX改善の最初のステップは、現状の課題やユーザーの本当のニーズを知るために「データ分析」と「ユーザー調査」を行うことです。具体的には、ユーザビリティテストやアンケートを通じて、以下の様な顕在的ニーズを把握します。
- 今まさに不便だと感じていること
- 改善してほしい要望
ユーザーインタビューや行動観察などを行うことで、ユーザー自身が気づいていない潜在的なニーズも掘り起こせます。この調査によって、なぜ離脱が起きているのか、どこにストレスを感じているのかといったUXの根本課題が浮き彫りになるため、改善の土台として最も重要なプロセスといえます。
ステップ②ユーザーの要求を整理する
調査で得られた情報は、そのままでは活かしづらいため、整理と構造化が必要です。例えば「上位下位関係分析法」を用いてニーズを階層化すると、「なぜその要望があるのか」「その背景にある根本課題は何か」が明確になります。
また、ペルソナを設定して代表的なユーザー像を描くことで、誰に向けた改善なのかを具体化できます。そしてカスタマージャーニーマップを作成し、ユーザーがサービスを利用する流れの中で「どこで迷うか」「どんな感情になるか」を時系列で整理しましょう。UX上の摩擦点やつまずきやすいポイントが浮き彫りになります。
この工程により、改善の優先度が高いポイントを的確に特定できます。
ステップ③課題に対するプロトタイプを作成
整理されたユーザー要求をもとに、実際に解決策を形にしていきます。この段階で大切なのは、完璧なデザインを目指すことではなく「素早く検証できる仮のUI」を作ることです。ワイヤーフレームやFigmaなどのツールを使ってプロトタイプを作成し、ボタンの配置、導線、文言、色合いなどを試しながら仮のUIを作ります。
この過程は、机上のアイデアを具体的な形にし、実際の利用イメージを確認できるため、後続の評価プロセスで実用的なフィードバックを得やすくなります。スピード重視で小さく試し、早めに修正できる状態にするのが成功のコツです。
ステップ④UX評価とユーザビリティ評価を実施
最後のステップは、作成したプロトタイプを実際のユーザーに使ってもらい、その体験を評価する工程です。評価は大きく2つに分けられます。
| 評価の種類 | 評価の内容 | 具体的な観点 |
|---|---|---|
| ①UX評価 | 利用中の感情や全体的な満足度を測る | ・使いやすいと感じるか ・また使いたいと思えるかなど |
| ②ユーザビリティ評価 | 操作性や達成度を数値的に測る | ・操作をミスなく完了できたか ・どのくらいの時間でゴールに到達できたか |
この二軸の評価を組み合わせることで、単に「便利そう」という印象だけでなく、実際の操作性まで含めた総合的な改善点を明確にできます。そして評価結果をもとに再度改善を繰り返すことで、完成度の高いUI/UXが実現できるのです。
アプリのUI/UXを改善するポイント
アプリのUI/UXを改善する3つのポイントを紹介します。
ポイント①ユーザーの理解を優先し実証的に改善する
アプリ改善は「ユーザーをどれだけ理解できるか」にかかっています。ペルソナ設計やユーザーインタビューを通じて、「誰に」「何の価値を」「なぜ提供するのか」を明確にすることで、アプリの方向性がブレずに済みます。また、机上で考えるだけでは不十分で、プロトタイプを実際にユーザーに使ってもらい、その操作感や不満点を観察することで、想定していなかった課題が明らかになります。
実際の声や行動に基づいて改善を繰り返すことで、机上の空論ではなく実証されたUI/UXが作れます。
ポイント②シンプルで明快なデザインを追求する
アプリの画面に情報や機能を詰め込みすぎると、ユーザーは「どこを押せばいいのか」「次に何をすればよいのか」が分からなくなり、結果として離脱につながります。
そのため「1画面1タスク」を意識し、必要以上の要素を並べないことが重要です。長い入力フォームは分割したり、ステップごとに必要な情報だけを表示したりすることで、ユーザーの認知負荷を減らせるのです。
複雑な機能を持つアプリであっても「迷わず操作できるか」という一点を優先して設計することで、初心者でも直感的に扱える優れたUXにつながります。
ポイント③一貫性・アクセシビリティを確保する
アプリ全体のUI要素が統一されていると、ユーザーは一度学んだ操作を他の画面でも迷わず活かせるため、スムーズに利用できます。フォント、色、ボタンの形や配置がバラバラだと直感的に操作できず混乱を招きますが、一貫したデザインはユーザーに安心感を与えられるのです。
また、操作に応じたフィードバックを取り入れることで、ユーザーは「正しく操作できた」と理解できます。結果としてアプリの評価や利用率向上にもつながります。
UI/UXを改善した事例
ここでは、アプリのUI/UXを改善した事例について3社紹介します。
| 企業名 | 課題 | 改善内容 | 効果 |
|---|---|---|---|
| Uber | 機能追加によるUI/UXの複雑化でユーザー体験が劣化 | ・ホーム画面から配車までのステップを見直し、不要なタップや確認画面を削除 | ・配車完了までの平均タップ数を20%削減 |
| スターバックス | ドリンクカスタマイズ画面が分かりにくい | ・カスタマイズ画面にアレルギー情報やトッピング選択を統合し、プレビュー機能を導入 | ・注文完了率が15%向上 |
| 株式会社リクルート | 転職者が職務経歴書の作成過程で迷いやすく、入力や操作に時間がかかる | 「初めてでも迷わず作成できる」コンセプトを設定し、プロトタイプ検証を実施。 | ・転職者がストレスなく経歴書を作成できるようになった |
事例①Uber
Uberは当初の「ワンタップで配車できる魔法」のようなシンプルさが、多数の機能追加によって複雑化し、ユーザー体験が劣化してしまった問題を抱えていました。そこでプロジェクトチームは、ユーザーの最も基本的な行動である乗車依頼にフォーカスし、改善を行いました。
まず、アプリのホーム画面から配車までのステップを徹底的に見直し、不要なタップや確認画面を削減して操作を最速化したほか、車種選択や支払方法の切り替えを直感的に行えるスライダーメニューを導入します。また、待機時間や到着予測の表示をリアルタイムで更新し、ユーザーが配車状況を一目で把握できるようにすることで、安心感と操作性を大幅に向上させました。
この再設計により、配車完了までの平均タップ数が20%削減され、ユーザー満足度が顕著に向上しています。
事例②スターバックス
スターバックスのモバイルアプリは、グローバルでの圧倒的なブランド力の一方で、ユーザーの不満も多く寄せられていました。
- ログイン時の操作の煩雑さ
- ドリンクカスタマイズ画面の分かりにくさ
- 注文処理中のエラー発生による決済離脱
そこで、デザインチームはまずユーザーの利用動向を分析し、特に48%のユーザーが非乳製品ミルクを選択する傾向に着目します。カスタマイズ画面ではアレルギー情報やトッピング選択をシームレスに行えるインターフェースを採用するとともに、ドリンクプレビュー機能を搭載し、選択内容の視覚的確認を可能にしました。
注文フローでは最終確認画面のレイアウトを整理して情報の優先度を見直し、アニメーションを用いたガイドで次のアクションを明確化します。これにより、注文完了率が15%向上し、アプリストアの評価も3.8へと改善されました。
事例③株式会社リクルート
株式会社リクルートが提供する「職務経歴書作成Webサービス」では、利用者が初めて使う際に入力方法や操作の流れが分かりにくく、途中で迷ってしまうことが多く見られました。特に転職活動を進めるユーザーは、限られた時間の中で効率的に書類を完成させたいというニーズがありながら、操作性の悪さが障壁になりました。
そこでリクルートは「初めてでも迷わず作成できる」というコンセプトを設定し、プロトタイプを用いた検証を重ねながら改善を実施します。行った施策は以下の通りです。
- ペルソナ分析を通じて利用者の課題を洗い出し
- ワイヤーフレームを用いた要件整理で構造を見直し
- スマートフォンでの利用を前提としたUI設計とアトミックデザインの導入
その結果、操作のしやすさが大幅に向上し、転職者が安心して利用できるサービスへと進化し、利用意欲の向上につながりました。
アプリのUI/UX改善はバルテス・イノベーションズまで
UI/UX改善は単なるデザイン刷新ではなく、ユーザー理解に基づく調査・設計・検証を繰り返し、継続的に成果を生み出すプロセスです。しかし、自社だけで体系的に進めるのは難しく、専門知識や客観的な視点が欠かせません。
バルテス・イノベーションズでは、ユーザーリサーチからプロトタイプ検証、開発フェーズにおける品質保証までワンストップで支援し、事業成果に直結するUI/UX改善を実現します。アプリやWebサービスの離脱率改善や顧客満足度向上に本気で取り組みたい方は、お気軽にご相談ください。
UI/UX改善ソリューション